出世がめちゃくちゃ遅い私は劣等生のワースト記録争いをすることは間違いないと思います。
おじさんになった今、自分を振り返ってみると落ちこぼれなのはそれなりの理由があったと感じます。私の経験から私みたいな落ちこぼれにならないためのポイント5をまとめました。
ここに分析して列挙するのは “こうあるべき”と偉そうなことを説教するのではなく、 私を振り返って恥を晒しますので、これを読んでいただける方にはさらに一歩進んでもらえるといいなと切に願っております。
1. 「仕事ができる」と余計に仕事を回されるという間違った考え方

経験談
入社数年目、上司や先輩から、次々と大きな案件を任されそれに応えようと必死に対応しました。しかし私の当時の考え方、実力と経験が追いつかず、結果として信頼を失う結果になりました。
改善策
- 仕事できる=いっぱい仕事を回されるではない
-
仕事ができると要求が高くなるがそれすらコントロール
-
信頼を勝ち取れば発言権が得られる
-
そこまでくれば仕事は自分がやりたいように回せる
若い当時の私は上司や先輩方が私を育てるために教えてくれているのではなく、使い勝手がいいから詰め込んでいるのでは?と思うようになってしまいました。
(とんでもない勘違い)
仕事出来ないと思われれば仕事がどんどん回ってこなくなると思った時期がありました。そうなると周りの期待から外れ難しい仕事を回されることがなくなりますが、その代わりにつまらない仕事が回ってきます。
“どうせ出来ないんだからあいつにやらせておけ”的な仕事しか回ってこないです。
仕事が出来ると発言権が与えられ、自分で仕事を決めることが可能。(言い換えればみんなを巻き込んで動いてもらう仕事)
“こうすればいいんじゃないか?”と自分のやり方で任せてもらえるようになります。
2. 「できない」を言えない弱み

経験談
当時の私は「頼まれたら断らない人が評価される」と思い込み、限界を超えて仕事を引き受けました。結果、納期遅延や品質低下につながり、逆に評価を落としました。
改善策
-
無理な案件は早めに相談
-
調整案(スケジュール変更・作業分担)を添えて断る
-
「Yes」より「How」を意識する
私は出来ない=弱音ではないということに気付くのが遅かったです。
出来ないと断ると“弱音を吐いている”と思われてしまうと思ってました。出来ない場合は自分の状況とどうすれば引き受けるか可能かの調整が出来ればいいんです。
それができれば相手(上司)も“その状況なら無理”と判断してくれたり、“そっちよりももこっちを優先して下さい”という指示が出せます。
上司は状況を言わないとわかってくれない人が多かったりもします。“出来ない”ということは罪ではなく、“出来る”と言ったにも拘わらず“出来なかった”方が大罪です。
3. 周りは敵ではなく無条件で全員味方

経験談
私の若い頃の考え方は〝周りを見返してやる〟であり、〝信頼を得る〟事はしませんでした。そのような状況ではたとえ良いことを成し遂げたとしても決して評価はされません。
改善策
-
周りの人は敵ではなく全員味方
-
味方の全体最適を考える思考へ切り替える必要がある
-
周りに対して至らなくても信頼を得る努力をする
-
見返りは決して求めない(必然的に後から返ってくるもの)
若い頃は先輩や同僚たちを“見返してやる!”という反骨精神を持っていました。若い頃に言葉イジりだったり、新人をかわいがる風潮があったのでそんなのを受けて“今に見てろ!見返してやる!”という気持ちがあったのかもしれません。そうなれば当然職場仲間とはうまくいっていませんでした。
現在の私は信頼を得る努力をしています。力は及ばないかも知れませんが職場の仲間を手助けになるよう心掛けています。
決して至らないかもしれませんが対応しようとする努力は見ていただけます。信頼が得られている状態であれば、例えば休憩していたとしても“あいつまた休憩してやがる”ではなく“疲れたから休憩しているんだね”という捉え方に変わることもあります。
そうなるまでには周りの人たちのために何をしてあげているか?という前段が必要です。
ここで重要なポイントは“決して見返りを求めてはいけない”ということだと思います。私はもっと早く顧客・上司・同僚・後輩からの信頼を沢山得ておけば良かったと切実に感じております。
4. 何事も「具体的に」「最後まで」を想定

経験談
私が足りなかったと思う重要なポイントの一つは“最後まで完遂することを想定すること”準備不足で相手からの信頼を失っていました。
改善策
-
依頼事項・業務など全てにおいて「具体的に」「最後まで」想定
-
①全体像を把握する②完了までを想像する
-
〝考えてくれている〟という印象を持ってもらう
私が足りなかったと思う重要なポイントの一つは“最後まで完遂することを想定すること”若い頃は、例えば出張に行く場合に出張先の最寄りの駅とその駅からどんなルートで最終目的地までいくという想像していました。
今では何出口でおりるから、何両目に乗った方がいいかまで想定します。
そういった想定をしておけば一緒に行った上司に“どこ駅がいちばんいい?”と聞かれた時に“〇〇駅の〇出口が一番近いです”と一歩先まで回答できます。そういった癖をつけておけば、資料を作って報告した場合でも質問された場合を想定して回答ができるようになり、相手(上司)からも〝先を読んで考えてくれている〟と感じてもらえます。
以前私は資料作成のゴールは作成でした。資料は作って終わりではなく、報告を理解してもらうまでが完了。
5. 超大事!「報連相」

経験談
言わずと知れた「報告・連絡・相談」若い頃の私は常に〝まだ言う時ではない〟の繰り返しで報連相ができていませんでした。よって相手から〝何をしてるの?〟〝何に時間かけてるの?〟と疑問を持たれるばかりでした。
改善策
-
報連相を制するものは仕事を制す
- 伝える内容とタイミングを図って信頼を得る
上司の立場も経験していますが、“部下は一体何を悩んでいるんだろう?”とか“何に一生懸命取り組んでるんだろう?”と言う不安を解消してくれる手っ取り早い方法が部下からの報連相です。
“私はここで迷ってます!”とか“これを一生懸命取り組んでます!”と宣言していただいただけで現状把握ができてしまいます。
若い頃の私は分が納得して完成するまでずっと報告せずに黙っている傾向があったので上司にとってとても恐ろしい存在だったかと思います。今のは私はガラス張りです。
“ここまで進んでます”や、“ここまで進んでるけどこれが原因で止まってます”という連絡はもちろんのこと“このままでは間に合わなくなります”という相談までサラッとしてしまいます。それによって気持ちがめちゃくちゃ軽くなりました。いやらしい話ですが上司に相談してしまえばボールは上司に渡ってしまいます。
まとめ:失敗は成長のタネになる
サラリーマンとして落ちこぼれを感じた経験は、当時は苦しくても後で振り返れば大きな学びになります。
大切なのは、失敗を放置せず改善行動に移すことです。
同じように悩んでいる方は、ぜひ今日から小さな改善を始めてみてください。
- 仕事は自分で回した方がやりたいようにできる
- 出来ないことは初めから出来ないと言おう
- 周囲を助けて信頼を得よう(最終的には自然に助けてもらえる)
- 仕事を完遂までシミュレーションしてみよう
- 報連相はしっかりやろう
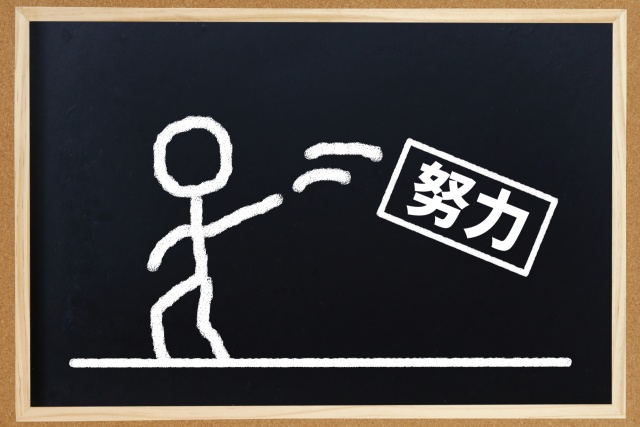






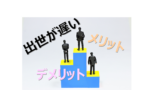
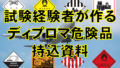
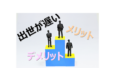
コメント