
はじめに
「会社にどうすれば評価されるのか」──これは多くのサラリーマンが抱える永遠の課題です。私も長年、評価されるための働き方を試行錯誤してきましたが、結果として評価が変わったのは「提案の質」を上げる習慣を持ったときでした。本記事では私が実践している3つの習慣を、具体的なやり方とともにお伝えします。
① 先を読む(“二手先”を常に想定する)

提案の成功率を高めるために最も重要なのは、相手の“次の動き”を先読みしておくことです。たとえば提出物を出すとき、私が意識するのは「自分が提出した後に上司や相手がどう反応し、どんな質問をしてくるか」を想定することです。想定問答を用意しておけば、実際に質問が来たときにすぐに答えられますし、「ここまで考えてくれている」という印象を与えられます。これは評価に直結しますし、ビジネスの現場でも有効だとされる方法です。
実践方法(私のやり方):
- 提案書・メールを出す前に「想定Q&A」を5分で書く。
- 可能な限り、相手の立場での問いを3つ想定しておく。
- 回答は簡潔にまとめ、資料の補足として付ける。
こうするだけで、確認のやり取りが減り、スムーズに合意に繋がることが多いです。
② 相手を知る(伝え方を相手仕様にする)
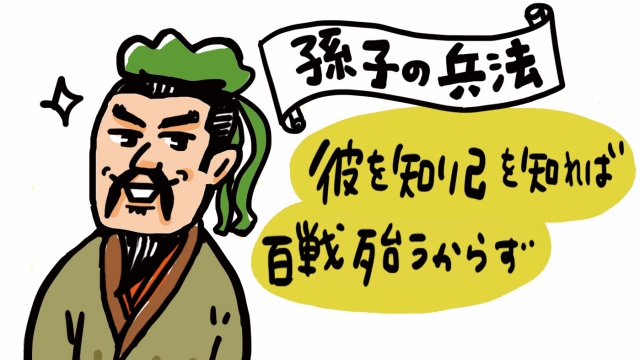
ビジネスは結局「人と人」の関係です。提案が刺さるかどうかは、相手(上司やクライアント)の好みやスタイルに依存します。細部が気になる人にはデータや根拠を中心に、大枠だけ見たい人には要点を先に提示する。こうした「合わせ技」を意識することで、読んでもらえる確率と理解度が大きく上がります。
実践方法(私のやり方):
- 初期のヒアリングで「好み」をメモする(詳細派/要点派/数字重視など)。
- 提案資料は冒頭に結論(要点)→裏付け(資料)の順に構成。
- 過去のやり取りを参照して、言葉遣いや報告の頻度を合わせる。
相手に寄せることで、提案が「受け入れられる形」になります。
③ 目的を理解する(依頼の“本質”を見抜く)

依頼されたタスクの表層的な要求だけを満たしていては、評価に結びつきにくいことがあります。重要なのは「なぜこの依頼が出されたのか(目的)」を確認することです。目的を押さえれば、依頼の延長線上で最良の提案が浮かびやすくなります。たとえば「売上を上げたい」という目的ならば、短期施策と中長期施策を分けて提示するなど、相手の成果志向に合わせた提案が可能になります。
実践方法(私のやり方):
- 依頼を受けたら「目的」を自分の言葉で要約し、確認する(口頭・メールどちらでも可)。
- 目的に沿って提案の軸を3つに絞る(効果・工数・リスク)。
- 目的達成のためのKPIや評価指標を一緒に提示する。
まとめ(今日からできる3つの習慣)
- 先を読む:提出物の後に来る質問を想定し、想定問答を用意する。
- 相手を知る:相手の好みに合わせて伝え方を変える。
- 目的を理解する:依頼の本質を押さえ、目的達成に直結する提案をする。
これらは特別な才能を必要としません。日々の習慣として少しずつ取り入れることで、あなたの提案は「受け止められる」ものになり、評価は自然と変わってきます。私自身もこの習慣で評価が変わり、仕事の幅が広がりました。ぜひ今日から一つだけ取り入れてみてください。
※参考・補足
- 提案力の評価指標や研修については企業内で体系化されている例が多く、実務的な改善施策も公開されています。



コメント